(旧岡崎家能舞台を生かす会 会長)
の
ようす

冒頭、能の歴史についてレクチャーいただきました。「650年の歴史ある能を引き継ぐのは私たちではなくみなさんだ」と話されていたのが印象的です。
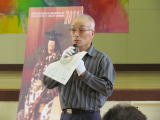
仮面劇、歌舞劇、楽器(笛・小鼓・大鼓・太鼓)、能舞台について詳しく説明を受けました。

特に仕舞は、教科書にも載っている「羽衣」ということで、参加した生徒たちにも興味深かったのではないかと思います。

1つ目は「能面講話コース」の様子です。
能面は130g程の重さで、木でできています。長ければ90分間、面を付けつづけても耐えられるように、薄く軽くしています。

持ち方から丁寧に指導を受けました。なかなか上手に持つことが難しいようでしたが、意外にも音を出すのは、うまくいっていました。

「昔はすぐに歌詞を覚えたもんだ」「みんな若いからすぐに覚えられる」と励まされながら、そして「恥ずかしがるな」と檄を受けながら、「羽衣」をみんなでうたいました。

舞う姿勢から指導を受けました。膝の使い方、上半身の身のこなしなど、なかなか普段にはない基本姿勢で、戸惑いがあったようです。

個別に音の出し方を教わりましたが、打楽器とは違って、扱いが難しいようでした。特に、空気の入れ方が難しいようで、なかなかきれいな音を出せなかったようです。

「オーゥ」「ヨォーゥ」の掛け声に合わせて、小鼓を打ちます。打楽器ということで、比較的簡単に音は出せていました。最後には、連続でリズミカルに合わせられていました。